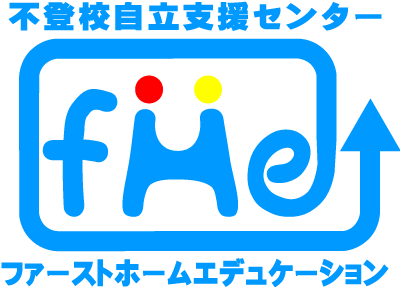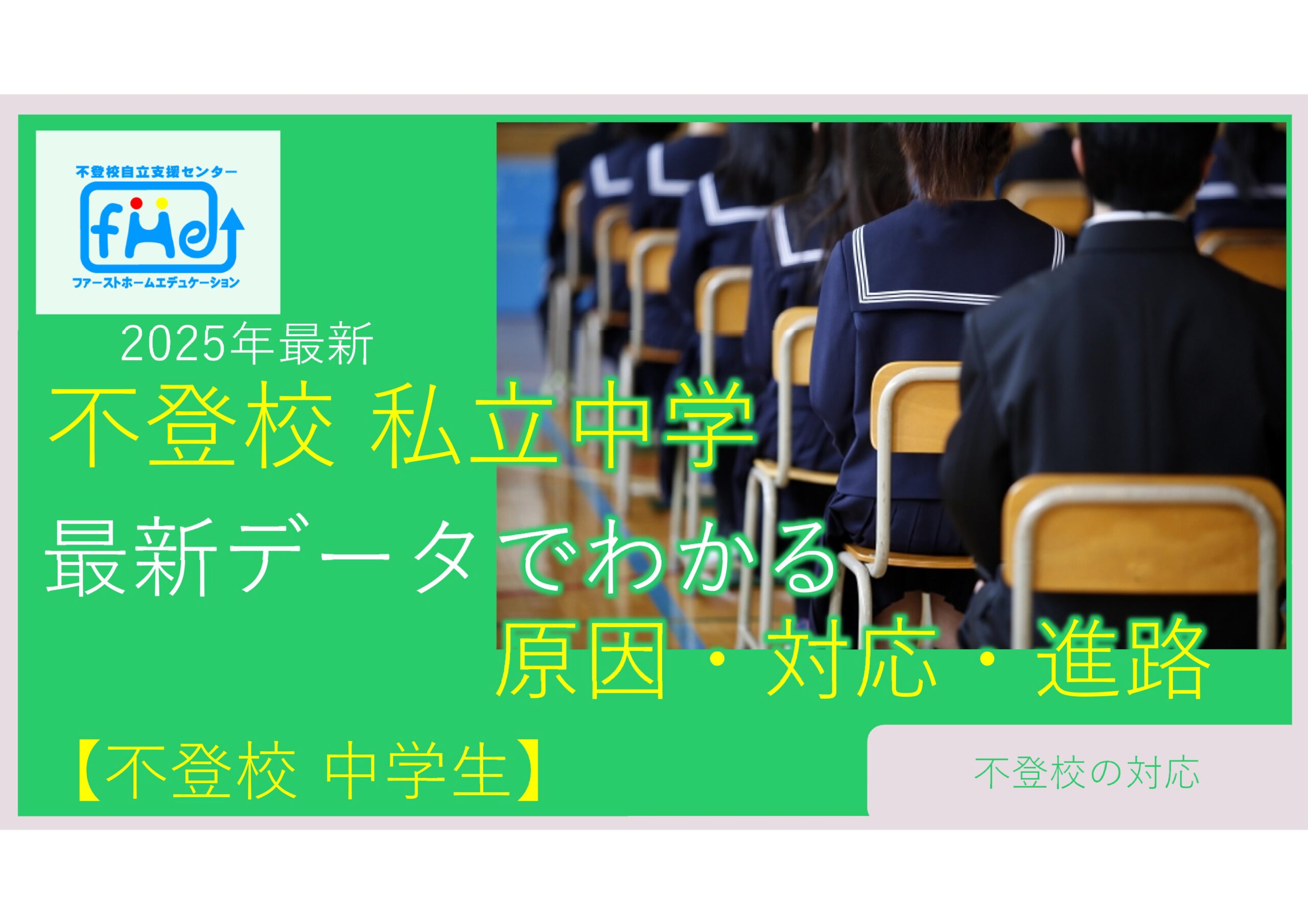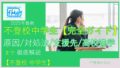私立中学や中高一貫校でも、不登校は年々増えています。
文部科学省の調査によれば、2023年度には全国で8,120人の私立中学生が不登校と報告されました。
難易度の高い学習、校風や校則の厳しさ、保護者の期待の強さ──こうした「私立・中高一貫校ならではの背景」が、不登校につながるケースは少なくありません。
この記事では、最新データ・原因・学年ごとの特徴・親の対応・支援先・進路選択までを専門家の視点で整理しました。
「どうすればわが子を支えられるのか」「進路はどうなるのか」という悩みに対し、実際に役立つ対応ステップを具体的に示していきます。
本記事を読めば、私立中学・中高一貫校における不登校の現状と対応の流れが1ページでわかります。
目次
第1章 私立中学の不登校とは?──定義と早期サインから見る実態
文部科学省の定義では「年間30日以上の欠席」=不登校とされます。 しかし現場では、「30日を待たずに出るサイン」を見逃さないことが何より重要です。
📊 最新データ:2023年度、私立中学の不登校生徒数は8,120人。 全国の中学生全体では約15人に1人が不登校となっています。 この数字は、2016年度比で約2倍に増加しています。
数字はあくまで全国的な把握のための目安です。 実際には、週2〜3回の欠席/朝の準備が進まない/保健室で過ごす時間が増える── こうした変化はすでに「助けが必要なサイン」です。
FHEの支援現場では、この段階で関わることで長期化を防ぐ確率が高まることが多く見られます。 つまり、「30日」という数字よりも、生活や感情の変化を見抜く力が大切です。
不登校の「予備期」に見られるサイン
- 欠席が点ではなく線になる(週2〜3回の欠席が続く)
- 朝の支度が進まない(起床できても動きが止まる)
- 学校の話題を避ける(家庭でタブー化し始める)
- 保健室や別室で過ごす時間が増える
- 生活リズムが崩れはじめる(昼夜逆転の兆し)
🚫 やってはいけない対応: 「30日を超えてから相談しよう」と先送りすること。 数字よりも早い段階の“変化”を見て、学校や専門機関へ早めに相談してください。
第2章 私立中学で不登校が増えている背景
私立中学・中高一貫校で不登校が増えているのは、「学力や校風」だけの問題ではありません。
社会・学校・家庭の構造変化が重なり、子どもが心身のバランスを崩しやすい環境が生まれています。
社会的な背景:コロナ禍以降、生活リズムの乱れや人間関係の分断が残り、社会的エネルギーの回復が追いつかない世代が増えています。
学校環境の変化も顕著です。
私立・中高一貫校では、授業進度の速さ、校則の厳格さ、期待の高さが重なり、適応の難しさを感じる子が増えています。
また、SNSでの比較や人間関係トラブルが心理的安全を脅かす要因となり、登校意欲を下げる傾向も見られます。
家庭の環境変化も無視できません。
共働き家庭の増加で「親が多忙で、子の悩みを受け止める余裕が減る」一方、「学費を払っている以上、頑張ってほしい」という無意識の圧力も働きやすい構造です。
この「家庭内期待の緊張」と「学校の高要求」が重なることで、中学生の心理的負荷は極めて高くなっています。
さらに、中高一貫校という構造的特徴も関係しています。
高校進学を見据えた環境で一度つまずくと、「この先もずっと苦しいのでは」と感じやすいのです。
学び続けるための「再スタートのルート」が見えにくいことが、不登校の長期化につながるケースもあります。
不登校が増えている主な背景まとめ
- コロナ禍の影響(生活リズム・人間関係の分断)
- 学校環境の高度化(進度・校則・比較文化)
- 家庭内の心理的緊張(期待と不安の両立)
- 中高一貫校構造(再出発ルートの見えにくさ)
- 社会的回復力の低下(エネルギー切れ世代)
FHEの支援現場でも、「学校+家庭」の二重構造が影響しているケースが多数を占めます。
子どもが「友人トラブル」と語っても、背景には学習の遅れ・家庭内プレッシャー・自己効力感の低下が絡み合っていることが多いのです。
第3章 私立中学の不登校の主な原因(7分類)
私立中学での不登校は「一つの原因だけ」ではなく、複数の要因が重なり合うケースが大半です。 ここでは代表的な7つの原因を整理します。
不登校の原因 7つの代表例
- 学習面のつまずき(授業進度が速くテストで挫折する)
- 人間関係のトラブル(いじめ・孤立・友人関係の変化)
- 思春期特有の心理(反抗期・自信低下・不安の高まり)
- 家庭環境の影響(夫婦不和・過度な期待・サポート不足)
- 入学直後の適応不全(中1ギャップ・燃え尽き)
- 身体的要因(起立性調節障害・睡眠障害など)
- 理由が明確でないケース(複合要因・説明困難)
FHEの支援現場でも「原因は一つに絞れない」ケースがほとんど。 例えば「友達と合わない」と言っていても、実際には学習面の遅れや家庭内の緊張が重なっていることが多いのです。
重要なのは「本当の原因探し」よりも「重なりを整理すること」。 家庭だけで抱え込まず、専門家と一緒に見立てることで対応の方向性が見えてきます。
注意: 「原因がはっきりするまで様子を見る」は危険です。 時間をかけすぎると、学習の遅れや社会的孤立が進んでしまいます。
第4章 学年別にみる不登校の特徴(中1・中2・中3)
不登校の傾向は学年ごとに大きく異なります。
中1は「環境変化」、中2は「停滞と人間関係」、中3は「進路不安」が主な焦点になりがちです。
中学1年生:環境の急変と「中1ギャップ」
小学校からの急な環境変化(授業のスピード/人間関係の再構築/部活動の開始)が重なり、受験後の燃え尽きも相まってつまずきやすい学年です。
朝の準備が止まる・保健室滞在が増える・学校の話題を避けるなどのサインが続いたら、早めの壁打ち相手(第三者)を確保すると長期化を防ぎやすくなります。
中学2年生:停滞が積み重なる学年
思春期の揺れ・反抗期・人間関係のもつれが重なりやすく、「やる気が出ないまま時間だけ過ぎる」停滞期型になりがちです。
家庭での声かけが説教化しやすいのもこの時期の特徴。責める・比べるは逆効果になりやすいので、短時間の成功体験(登校前の準備だけ/教科書を開くところまで 等)を積み上げる設計が有効です。
👉 中2不登校の詳細を見る(※公開後にURL差し替え)
中学3年生:進路不安と「行きたいけど行けない」葛藤
受験・将来の選択が目前となり、「行けないと不利になるのでは」という不安が強くなります。
再登校のタイミングと入試準備をどう結びつけるかが鍵。家庭・学校・支援者で同じ目標(全日復帰/出願戦略 等)を共有すると、短期間での一気の全日復帰が現実的になります。
👉 中3不登校の詳細を見る(※公開後にURL差し替え)
FHEの基本方針:学年ごとに支援の優先順位を変えます。
中1=安心感と自己肯定感の回復/中2=停滞打破の仕掛けと家庭支援/中3=進路と自己効力感の連動設計。
注意:「様子を見る」を長引かせると、学習の遅れ・孤立・生活リズムの崩れが固定化しやすくなります。
サインが数週間続く場合は、学校や専門家に早めに相談しましょう。
関連記事|学年別の不登校対応をさらに詳しく知りたい方へ
各学年ごとの特徴と具体的な対応を、実例とともに解説しています。
▶ 中学1年生:入学初期のギャップと、回復に向けた家庭内の整え方。
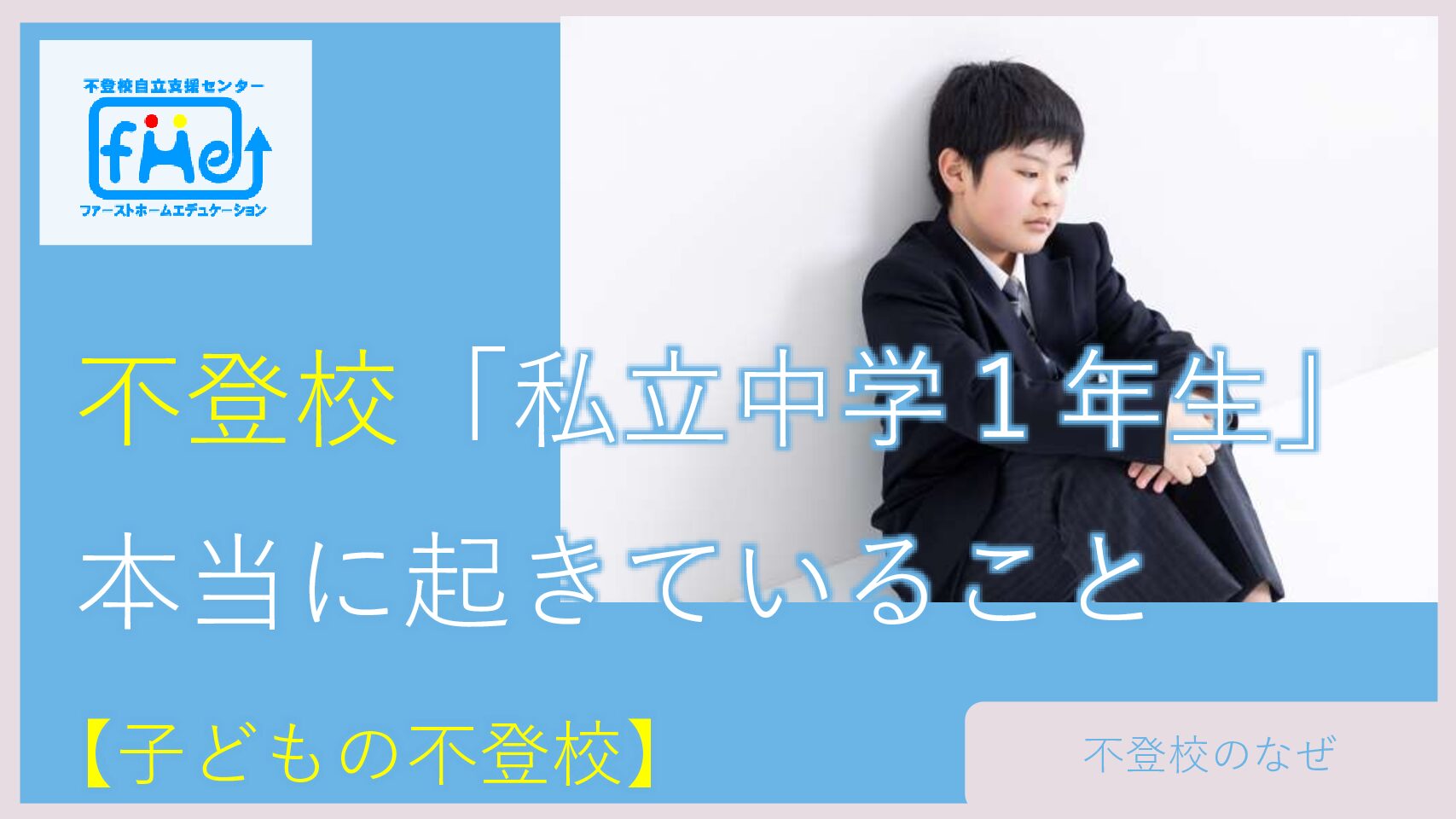
▶ 中学2年生:「変化のなさ」「停滞期」からの突破口と親の関わり方。
▶ 中学3年生:進路・高校選択と、再登校のタイミング設計。
学年別の違いを押さえたら、 次は「中学生全体の傾向と回復の共通ステップ」を俯瞰して比較しましょう。
🔍 “全体像”で分かること: 傾向/初期対応の優先順位/回復パターン
第5章 不登校のサインと初期対応
不登校は「突然」始まるのではなく、必ず前兆があります。
そのサインに早く気づき、初期対応を正しくとることで長期化を防げる可能性があります。
不登校のサインに気づくポイント
- 朝の準備が進まない(着替えや登校準備が止まる)
- 体調不良を頻繁に訴える(頭痛・腹痛・倦怠感など)
- 欠席が週に数回出始める(点ではなく線になる)
- 家庭で学校の話題を避ける(話すと不機嫌になる)
- スマホ・ゲームに没頭(生活リズムの乱れの兆候)
初期対応の基本は「無理に登校させない」ことですが、同時に「生活を崩さない」ことも大切です。
欠席によって心身を休ませる効果はありますが、それを遊び時間にしてしまうと、学校に戻るハードルが高くなることが研究でも示されています。
文部科学省および国立教育政策研究所の調査では、長時間の動画視聴やネットゲームは一時的な気晴らしになる一方で、身体的疲労や姿勢固定によるストレスを増大させることが報告されています。
体を動かさず視覚刺激を受け続けることが、副交感神経の働きを抑制し、倦怠感・不安感を強める傾向があると指摘されています(文科省「子どもの健康と生活習慣」2023)。
また、生活リズムの「規則性(orderness)」が学習意欲・情緒安定・社会的つながりの維持に関与することも複数の研究で示唆されています。
つまり、休ませながらも学校生活に戻れる軌道を残す家庭作りが重要なのです。
親ができる初期対応ステップ
- ステップ1|休ませるが「生活リズム」を崩さない(起床・食事・就寝を学校時間に近づけて保つ)
- ステップ2|過度な“娯楽時間”を避ける(長時間の動画・ゲームは控え、体を動かす活動へ切り替え)
- ステップ3|外部とつながりを残す(学校・専門家・支援先に早めに共有する)
FHEの支援現場では、「休息」と「行動」の両立が重要と考えます。 単に安心させるだけでなく、小さな成功体験を積み重ねながら“次の一歩”を可視化する支援が、再登校や社会的自立の基盤になります。
🚫 やってはいけない対応:
・「怠けているだけ」と決めつける
・長時間の動画やゲームを放置する
・「30日を過ぎたら相談」など先延ばしにする
第6章 親がやってはいけない対応/有効な対応
親の対応は、子どもの回復スピードに大きな影響を与えます。
ここでは「やってはいけない対応」と「有効な対応」を整理し、さらにFHEが大切にしている家庭支援の視点を紹介します。
やってはいけない対応
- 強引に登校させる(不安が増し、家庭が安心の場でなくなる)
- 怠けていると決めつける(自己肯定感を大きく下げる)
- 叱責や説教を繰り返す(安心よりも緊張を与えてしまう)
- 支援を子ども任せにする(家庭が孤立化し、回復が遅れる)
有効な対応
- 安心できる家庭環境を整える(叱責より受容を優先)
- 生活リズムをできる範囲で保つ(起床・食事・就寝)
- 子どもの気持ちを言葉にできる場をつくる(傾聴と共感)
- 学校や専門家と早めに相談する(家庭だけで抱え込まない)
FHEの支援現場で多い誤解は「見守っていれば自然に回復する」という考え方です。
実際には安心だけでは停滞を招きやすく、安心+行動のきっかけが必要になります。
FHEでは、家族療法(Minuchin, 1974)や動機づけ面接(Miller & Rollnick, 2013)の理論を基盤に、
訪問カウンセリングを通じて家庭内から“行動のスイッチ”を作る支援を行っています。
家庭の支援スタンスが変わるだけで、子どもの回復は大きく前進します。
「休ませるか行かせるか」の二択ではなく、休ませながら外の世界とつながる準備を整えること。
その具体的な伴走を専門機関と一緒に進めていくのが、回復への近道です。
第7章 支援先・居場所の選び方と注意点
大切なのは「どこへ通うか」ではなく、子どもが安心して続けられる環境をどう作るかです。
私立・中高一貫では制度や在籍の扱いが公立と異なるため、メリット/リスク/出口(再登校・転学・進路)を同時に考えると失敗が減ります。
主な選択肢(役割と向き・不向き)
- フリースクール:安心感と人との再接続が目的。学びの再始動に有効。向き:教室が強い不安刺激。不向き:明確な復学時期を決めたいケース。
- 教育支援センター(適応指導教室):自治体設置。学校復帰の橋渡しに特化。向き:段階的準備。不向き:通所自体が負担な段階。
- 保健室・別室登校:学校と接点維持。向き:校内刺激の調整。注意:長期の“居場所化”で停滞しやすい。
- オンライン学習:リズム維持と学び直し。向き:在宅が安全基地。注意:昼夜逆転の温床にならない設計が必要。
- 家庭教師・塾:学習遅れの補填。向き:学力要因が主。注意:心理的準備が不足のままは逆効果。
- 不登校特例校:少人数・柔軟カリキュラム。向き:集団規模の縮小が必要。注意:通学圏や入学要件。
- 訪問型支援:専門家が家庭に入り、安心+行動のスイッチを作る。向き:外出困難・初期立て直し。
選び方の基準(Fit-Firstマトリクス)
- 安心の持続:その場に毎週(できれば毎日)通える見込みはあるか?
- 生活リズム:起床・食事・就寝が学校時間帯に近づく運用になっているか?
- 出口設計:再登校/転学/進路のいずれにどう接続するか、期日・条件を決めているか?
- 家庭の負荷:送迎や費用、親の心理的余力と両立できるか?
中高一貫校ならではの注意点
- 在籍と学費:不登校でも在籍=学費負担が原則。減免・猶予の制度は学校へ早期相談。
- 進度差:中3で高校課程に入る学校も。外部受験・転学の際は学習範囲のズレを要確認。
- 再スタートの設計:クラス替えや環境変更が少なく、「見切りポイント」(例:学年末までに◯◯が整わなければ転学検討)を決めると迷走を防げる。
よくある失敗と回避策
・「居場所=ゴール」化してしまう → 出口(学校・転学・進路)と期日を先に決める。
・長時間の動画・ゲームで昼夜逆転 → 学校時間の生活リズムを優先し、在宅でも“活動の時間割”を設定。
・家庭だけで抱え込む → 学校・専門家と早期に情報共有。訪問支援で「安心+行動」の同時進行。
ミニQ&A
Q:居場所に通わせれば自然に戻れますか?
A:安心は必要条件ですが十分条件ではありません。生活リズムと出口設計(再登校・転学・進路)を同時に設けると、戻りやすくなります。
Q:在宅中心での回復は可能?
A:可能です。学校時間帯の生活・家庭内対応(どの程度どのように介入するのか)を本人の傾向,状況にあわせてプランニングを組み合わせ、“活動の時間割”を作るのがポイントです。
第7章 支援先・居場所の選択肢
不登校の子どもにとって、家庭以外の「居場所」を確保することは大きな支えになります。 支援先にはさまざまな種類があり、それぞれ役割や特徴が異なります。
代表的な支援先・居場所
- フリースクール:学びと交流の場。安心感を重視。
- 教育支援センター(適応指導教室):自治体が設置。学校復帰を目的とした支援。
- 保健室登校:教室に入れなくても、学校との接点を維持。
- オンライン学習サービス:家庭から学習習慣を支える。
- 家庭教師・塾:学習遅れを補う。ただし無理強いは逆効果。
- 不登校特例校:少人数・柔軟なカリキュラムのある公立校。
- 訪問型支援:家庭に専門家が入り、安心と行動を同時に支える。
家庭に合う居場所の見極めが重要です。 「どの支援先が合うか」=「どこなら安心できて続けられるか」を基準にすると、長期化を防ぎやすくなります。
ただし、安心できる居場所に通うこと=ゴールではありません。 最終的には学校復帰・進路選択・社会との接点にどうつなげるかを考える必要があります。
近年は代替教育(オルタナティブ教育)の選択肢も増えましたが、 「学校教育に向かない=学校を否定してよい」という意味ではありません。 実際に、文部科学省の不登校経験者調査では、 「行けばよかった」37.8%が最多で、「しかたがなかった」30.8%を上回っています。
不登校当時をふり返ってどう思うか(経験者調査)
- 行けばよかった:37.8%
- しかたがなかった:30.8%
- 行かなくてよかった:11.4%
- 何とも思わない:17.0%
=「行けばよかった」が最多。 学校に戻る(転学を含む)可能性を初期から閉ざさないことが、 子どもの将来の選択肢を広げる支援につながります。
出典:文部科学省「不登校に関する実態調査報告書」(2014) 有効回答1,556/行けばよかった37.8%・しかたがなかった30.8%・行かなくてよかった11.4%・何とも思わない17.0%
FHE(ファーストホームエディケーション)では、 訪問カウンセリングや家族療法を通じて、家庭の安心と再登校の可能性を両立する支援を行っています。 子どもが社会とつながるための選択肢として、学校・転学・別の学びのいずれにも開かれた支援設計を行います。
第8章 まとめ:不登校からの回復を支える家庭の力
不登校は「家庭の努力が足りない」ことではありません。 子どもの中で起きているのは、心と体がこれまでの環境に適応できなくなったというSOSのサインです。 そのサインを受け止め、支えることから回復が始まります。
これまでの章でお伝えした要点
- 第1章: 不登校は「30日を待たずに始まる」──早期サインの発見が鍵。
- 第2章: 私立中学では「学習・人間関係・価値観」の三重ストレスが要因。
- 第3章: タイプ別に見ると、原因よりも「背景の構造」を見極めることが重要。
- 第4章: 家庭の安定が第一歩。親が安心しているほど、子どもは動き出せる。
- 第5章: 初期対応で生活リズムを守ることが、長期化防止の最も有効な手段。
- 第6章: 「安心+行動のきっかけ」──FHEの支援が重視する回復メカニズム。
- 第7章: 代替教育・支援先の選択は、最終ゴールではなく「つなぐ過程」。
大切なのは、「一人で抱え込まない」こと。
家庭での見守りと専門家の伴走を組み合わせることで、子どもが再び外の世界とつながる力を取り戻せます。
家庭ができる3つの行動指針
- ① 状況を客観的に整理する:学校・家庭・本人の状態を分けて捉える。
- ② 家庭内の安心を保つ:否定や焦りより「今を受け入れる」姿勢を意識。
- ③ 行動のきっかけを設計する:無理なく外とつながれる環境(訪問・通信・短時間登校など)を整える。
藤本琢(公認心理師/FHE代表)より
「不登校の支援は、“見守る”か“動かす”かの二択ではありません。
FHEでは、安心を土台にしながらも行動を生む支援──家庭から始まる回復のデザインを大切にしています。」
よくある質問(Q&A)
保護者の方からよく寄せられる質問をまとめました。
「在宅中心での回復」「学校との連携」「進路・再登校の考え方」など、
実際の支援現場で多いご相談を簡潔に解説します。
Q1:在宅中心での回復は可能?
A:可能です。ただし、「家庭内でどう過ごすか」が重要になります。
学校時間帯の生活リズムを保ちながら、本人の傾向や状況に合わせて、どの程度・どのように介入するかをプランニングすることが大切です。
FHEでは、在宅期から少しずつ行動の幅を広げるために、家庭内対応と訪問支援を組み合わせた“活動の時間割”づくりを行っています。
Q2:学校との連携はどうすればいい?
A:不登校初期では、担任やスクールカウンセラーに「現状共有」から始めるのが良いでしょう。
登校刺激を強めるよりも、安心して話せる関係を維持することが大切です。
FHEでは、家庭と学校の間に立ち、段階的な連携プランを設計しています。
Q3:中高一貫校で不登校。外部受験は不利?
A:学校によっては、中3時点で高校課程が始まっていることもあり、
学習範囲のズレ対策が必要です。
また、内部進学が前提の学校では転学や外部受験が想定されていない場合もあります。
👉 詳しくは第8章「不登校と進路」で解説しています。
Q4:家庭でできる支援と専門機関の違いは?
A:家庭では「安心のベースづくり」と「声かけ・日常支援」が中心です。
一方、専門機関では、行動変容・心理面の支援・家庭内関係の調整などを専門家が行います。
どちらか一方ではなく、家庭×専門家の二軸支援が効果的です。
Q5:復学支援を受けるタイミングは?
A:欠席が2〜3週続いた時点が目安です。
本人の調子を見ながら早期に相談することで、「長期化を防ぐ支援」が可能になります。
FHEでは、初期のご相談から家庭訪問・学校連携まで一貫してサポートしています。
参考文献・データ出典
- 文部科学省(2024)『児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査』
- 文部科学省(2023)『不登校児童生徒への支援の在り方に関する検討会議 報告書』
- 内閣府(2022)『子供・若者白書』第2部 不登校児童生徒の状況
- 厚生労働省(2023)『生活習慣とメンタルヘルスに関する実態調査報告書』
- 日本財団(2023)『不登校の実態調査2023:家庭・学校・支援機関の相互関係』
- 国立教育政策研究所(2022)『教育課程実施状況調査(中学校)』心理的ストレス要因分析
- 東京大学大学院 教育学研究科(2022)「在宅時間と心理的ストレスの関連に関する調査報告」
- 国立精神・神経医療研究センター(2021)『思春期のストレス反応と不登校傾向に関する研究』
- OECD(2023)『Students’ Well-being and Learning Environment(PISA2022報告書)』
- UNESCO(2021)『Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education』